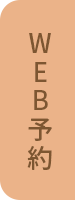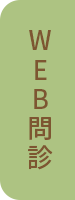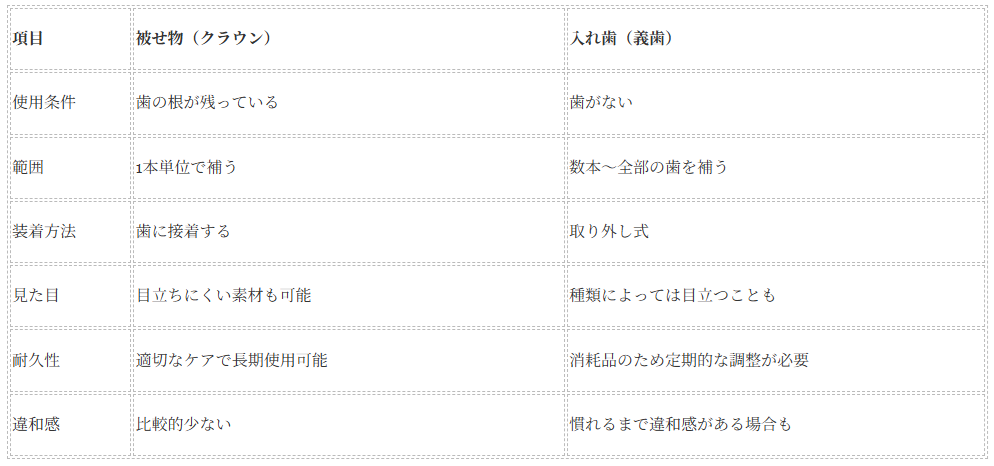こんにちは!高澤歯科クリニックです。
インプラント治療は、失った歯を補う方法として広く知られています。しかし、すべての方が必ず受けられる治療というわけではありません。安全に治療を行うためには、お口の状態だけでなく全身の健康状態も大きく関わります。今回はインプラントができない人とはどんな人かについてご紹介します。
■全身の病気がコントロールされていない場合
インプラントは外科処置を伴う治療のため、体の治癒力がとても重要です。重度の糖尿病がコントロール不良のまま続いている方は、傷の治りが遅く感染リスクも高まるため、すぐにインプラントを行うことが難しい場合があります。また、重い心疾患や脳血管疾患がある方、免疫力が大きく低下している方なども慎重な判断が必要です。ただし、病気があっても主治医と連携し、状態が安定していれば治療が可能になるケースもあります。
■あごの骨が極端に少ない場合
インプラントはあごの骨に人工歯根を埋め込む治療なので、骨の量と質がとても重要です。歯を失ってから長期間そのままにしていると、骨が痩せて薄くなってしまうことがあります。骨の厚みや高さが不足している場合、そのままではインプラントが安定しません。ただし、骨を増やす処置(骨造成)を併用することで対応できることもあり、必ずしも不可能とは限りません。精密な検査による診断が大切です。
■お口の環境が整っていない場合
重度の歯周病が進行している方や、日々の歯みがきが十分にできていない方も、そのままではインプラント治療はおすすめできません。インプラントはむし歯にはなりませんが、歯周病に似た「インプラント周囲炎」になることがあります。これは周囲の骨が溶けてしまう怖い病気です。治療前に歯周病のコントロールやブラッシング習慣の改善が必要になります。
■生活習慣や通院が難しい場合
喫煙習慣がある方は、血流が悪くなることで傷の治りが遅れ、インプラントの成功率が下がるといわれています。また、治療後は定期的なメンテナンスが欠かせないため、通院が難しい方も慎重な判断が必要です。インプラントは入れて終わりではなく、長く使うための管理がとても重要な治療なのです。
■まとめ
インプラントが「できない」と言われる背景には、全身の健康状態、骨の状態、お口の環境、生活習慣などさまざまな要因があります。しかし、多くの場合は適切な治療や準備を行うことで可能になる道もあります。
当院では患者さまの状態やご希望に合わせて、安心・安全な治療をご提供しています。インプラント治療について詳しく知りたい方は、どうぞお気軽にご相談ください。