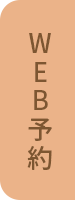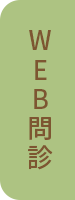こんにちは!高澤歯科クリニックです。
「子どもの矯正って本当に必要なの?」とお考えの保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、歯並びは成長とともにある程度整ってくる場合もありますが、「今しかできない治療」もあるのです。
今回の記事では、成長期の子どもだからこそ効果が期待できる矯正治療「プレオルソ」についてご紹介します。
■「プレオルソ」は成長の力を活かして歯並びと噛み合わせを整える
プレオルソは、子どもの成長期に合わせて使用する「マウスピース型矯正装置」です。
骨格がまだ柔らかいこの時期に使用することで、顎の発達をサポートしながら、正しい歯並びと噛み合わせへと導いていきます。
噛み合わせがズレていると、食べ物をしっかり噛めなかったり、将来的に顎や顔のゆがみ、頭痛、肩こりといったトラブルに繋がることもあります。
■「呼吸」や「姿勢」の改善にも効果がある
プレオルソは、単に歯を動かすだけでなく、口周りの筋肉のバランスや舌の正しい位置、鼻呼吸の習慣づけなど、
「お口の機能」を整える働きもあります。実際、口呼吸がクセになっているお子さまは、歯列の乱れや姿勢の悪化にもつながることが多く、
集中力の低下やいびきの原因になることもあります。こうした問題の改善も期待できます。
■将来の虫歯予防にも
歯がガタガタに並んでいると、どうしても歯ブラシが届きにくくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
プレオルソによって歯列が整えば、日々の歯磨きもしやすくなり、セルフケアの精度もアップします。
子どものうちから清潔な口腔環境をつくることで、将来のトラブル予防になります。
■子どもの自信にもつながる矯正治療です
見た目を気にして笑えなかったり、人と話すことをためらうなど、歯並びの悩みが、子どもの自信に影響することも少なくありません。
プレオルソは見た目を自然に整えるだけでなく、「笑顔に自信が持てるようになる」「自分に自信がつく」といった心理的な効果も期待できます。
こうした変化が、学校生活や友人関係にも良い影響をもたらします。
■プレオルソはいつ始めるのがベスト?
プレオルソの治療は、6〜12歳頃の「混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)」に始めるのが理想的です。
この時期は成長スピードも早く、骨の変化に柔軟に対応できるため、よりスムーズな矯正が可能です。
また、早期に始めることで将来的に大がかりな矯正や抜歯の必要がなくなるケースもあります。
■まとめ
「プレオルソ」は、子どもの成長を最大限に活かしながら、歯並びだけでなく呼吸や姿勢、口腔機能全体を整えるための矯正治療です。
当院では、お子さま一人ひとりの状態を丁寧に診断し、相談に応じています。気になる方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。